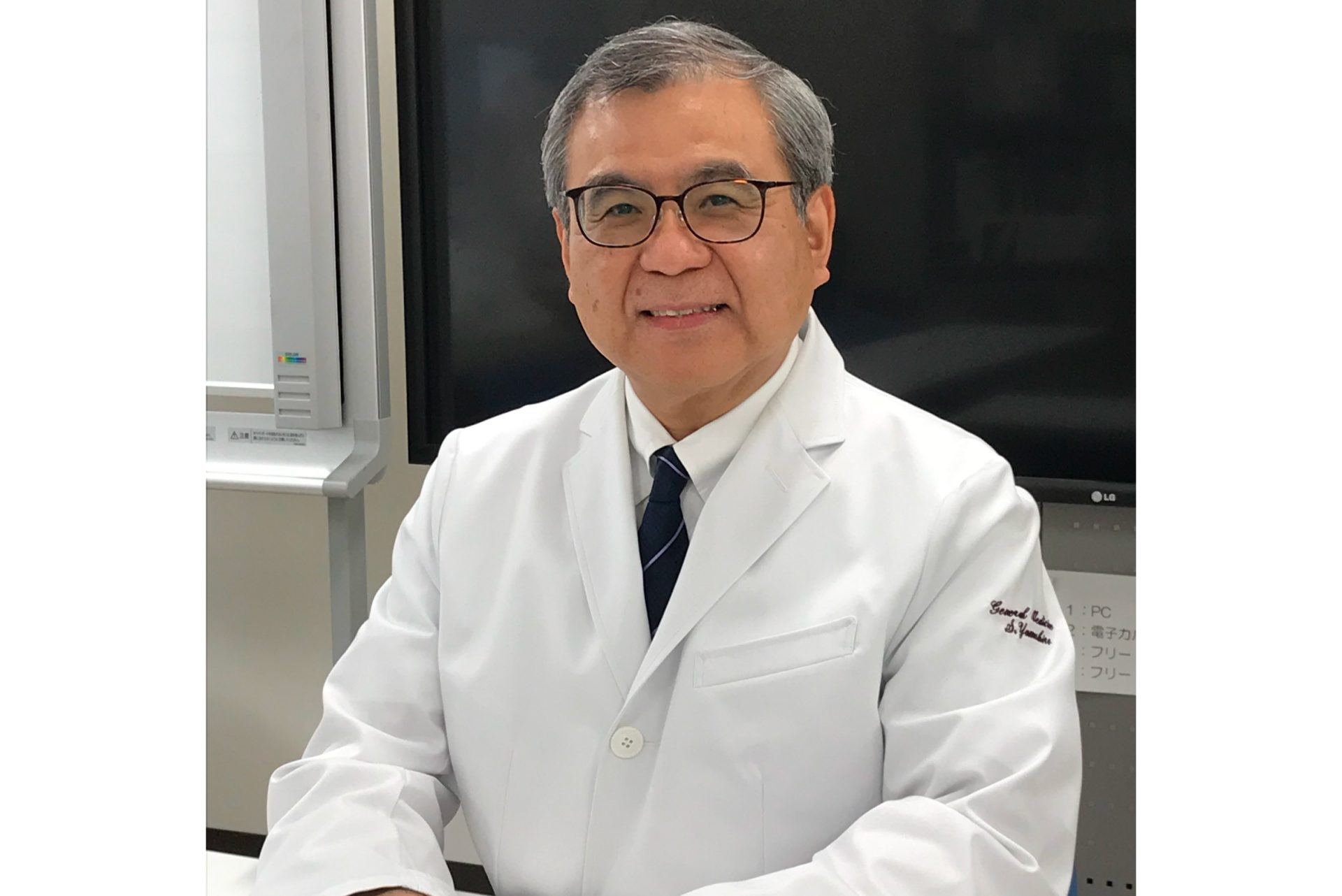キャリア 2025.08.29
総合診療医・山城 清二さんのあゆみ
以和貴会西崎病院 病院長 山城清二先生
富山県南部・世界遺産 白川郷で知られる南砺市(なんとし)は、かつて医療崩壊の危機に直面していました。医師としての熱い思いとこれまでの臨床経験を生かし、地域医療再生という大きなプロジェクトに立ち向かった医師がいます。今回は、現在、沖縄県の西崎病院で病院長を務める山城 清二(やましろ せいじ)さんに、医師を目指したきっかけ、総合診療を専門にするまでの経緯、そして富山大学での取り組みについて伺いました。
総合診療を専門とするまで
父の病きっかけにサッカー少年、医師を志す
私が医師を志したのは、父が病に倒れたことがきっかけでした。私は沖縄県那覇市で生まれ、父の仕事の関係(教師から建築関係へ)で東京で育ちました。サッカーに打ち込み楽しい学校生活を送っていたのですが、高校1年の冬休みに生活が一変しました。父がくも膜下出血で倒れ大学病院で手術を受けたのです。幸いにして手術は成功しましたが、術後は言語障害やけいれん発作に悩まされ、仕事への復帰はかないませんでした。この頃、母から「5人兄弟の中から1人でも医者になってほしい」と懇願されたのです。父は建築関係の仕事をしていたこともあり私もその道に進もうと思っていたのですが、高校3年になって志望を医学部に変更しました。担任の先生には「大丈夫か」と心配されましたが、3年間の浪人を経て、晴れて佐賀医科大学(現在の佐賀大学医学部)へ合格しました。
医学部に進んでからは、どのような医師になろうか将来を模索しました。「父がくも膜下出血だったので脳外科医になろうか」と思ったり、サッカーの経験を生かして「スポーツドクターになろうかな」などと思ったりしました。迷った末に、脳血管障害の予防という観点から地域医療に関心を持つようになりました。友人の紹介で菊池養生園診療所(熊本県菊池市)の竹熊 宜孝(たけくま よしたか)先生に出会い、医・食・農の視点から「土からの医療」を学びました。竹熊先生は東洋医学にも精通しておられましたが、意外なことに「沖縄出身なら沖縄県立中部病院(沖縄県うるま市)でまず西洋医学をしっかり学びなさい」と助言をいただいたのです。
離島での経験、そして留学へ
大学卒業後に赴任した中部病院は救急患者が多く、まるで野戦病院のようでした。当時、中部病院では米国式の卒後臨床研修を行っていました。1年目はインターンとして、2年目からは内科各科をローテーションし、4年目は救急を担当して忙しく過ごしました。5年目には沖縄県立八重山病院(沖縄県石垣市)に派遣され、総合内科医として勤務しました。内科一般の診療のほか、救急搬送や離島の診療所の応援をしながら、在宅医療にも関わり始めました。自宅での介護が難しいなどの理由から長い間社会的入院をされていた患者さんがとても多かったため、自宅に帰れるよう支援するためです。振り返ると、このときの石垣島での経験が総合診療を専門にする道への出発点になったのだと思います。6年目からは中部病院に戻り、救命救急センターで勤務しました。
そして10年目、佐賀医科大学医学部附属病院(現在の佐賀大学医学部附属病院)に、国立大学では初めてとなる総合診療部が設置されることになったのです。私にも声がかかり、1993年に母校へ移りました。総合診療部の立ち上げを手伝う日々のなかでは、それまで沖縄で経験してきた救急や離島、地域医療の経験が大いに役立ちました。初代教授である福井 次矢(ふくい つぐや)先生からは英語で論文を執筆する機会をいただき、留学経験のある先生の姿に大変刺激を受けました。そして、1995年から2年間カナダのトロント総合病院で総合診療を、その後アメリカに移り1年間ハーバード大学大学院で公衆衛生を学びました。帰国後は佐賀大学に戻り、医学教育やEBM(Evidence-based Medicine、エビデンスに基づく医療)の教育、研究、地域医療などに取り組みました。医学教育については、二代目教授である小泉 俊三(こいずみ しゅんぞう)先生からアドバイスがあり、ハワイ大学での研修も受けました。
富山大学での日々
県南西部・南砺市の医療崩壊
そして2004年、富山医科薬科大学附属病院(現在の富山大学附属病院)に総合診療部が設置されることになり、初代教授に就任しました。富山大学では社会的なニーズが高い家庭医/総合医の育成を目指しました。そのために、家庭医療(Family Medicine)、総合内科(General Internal Medicine)、救急(Emergency Medicine)、そして医学教育の充実に取り組むことにしたのです。
時期を同じくして新医師臨床研修制度が導入され、岐阜県飛騨市や白川村と隣接する県南西部の地域では4町4村が合併して南砺市が誕生しました。当時、南砺市には市立病院が3つ、診療所が4つありましたが、新たな研修制度の開始と市町村合併の影響が相まって医師不足が深刻化し、2007年頃から医療崩壊が始まったのです。医療提供体制の整理が進められるなかで、南砺地域の病院の院長から大学にいた私に「(地域医療再生を)手伝ってくれないか」と声がかかりました。
報道や書籍などで他県の取り組みを調べ、対策は「地域で医療人材を育成する仕組み」と「住民参加型の地域医療システム」を作るしかないとの結論に至りました。地域社会には、政治、経済、文化、そして健康とさまざまな側面があります。医療従事者の役割は、地域医療や地域保健を通じて健康的な側面を支えることですが、それぞれの側面は互いに関連しています。そして、最終的な目標はその地域の住民が幸せに暮らすことなのです。
地域での人材育成と住民参加型の医療システム
2007年には、南砺地域にあった病院の1つが診療所化されることになりました。この診療所は、トロント大学の家庭地域医療部にアイデアを得て、医療人材を育成するセンターという意味で、「南砺家庭・地域医療センター」と名づけました。地域に根ざし、地域住民の健康的な生活を支える拠点として、南砺地域の病院や富山大学とも連携しながら、外来だけでなく訪問診療も行いました。当時、全国の大学医学部教授で訪問診療を行っていたのは私くらいだったかもしれません。楽しくやりがいのある日々だったと今でも懐かしく思い出します。
同時に南砺市の各地をまわって、住民を対象に病気や地域医療の課題についてセミナーを開催しました。当初はセミナーを受講した住民が、自ら課題をみつけて行動を始めてくれることを期待していたのですが、2年が経過してもその兆候はみられませんでした。参加者からは「自分たちも何かしなければならないことは分かったけれど、どのように行動したらよいのか分からない」との意見があがり、意識は変わりつつあるものの行動の変化には結びついていないことが伺えました。
※山城さんのインタビュー後編はこちらのページをご覧ください