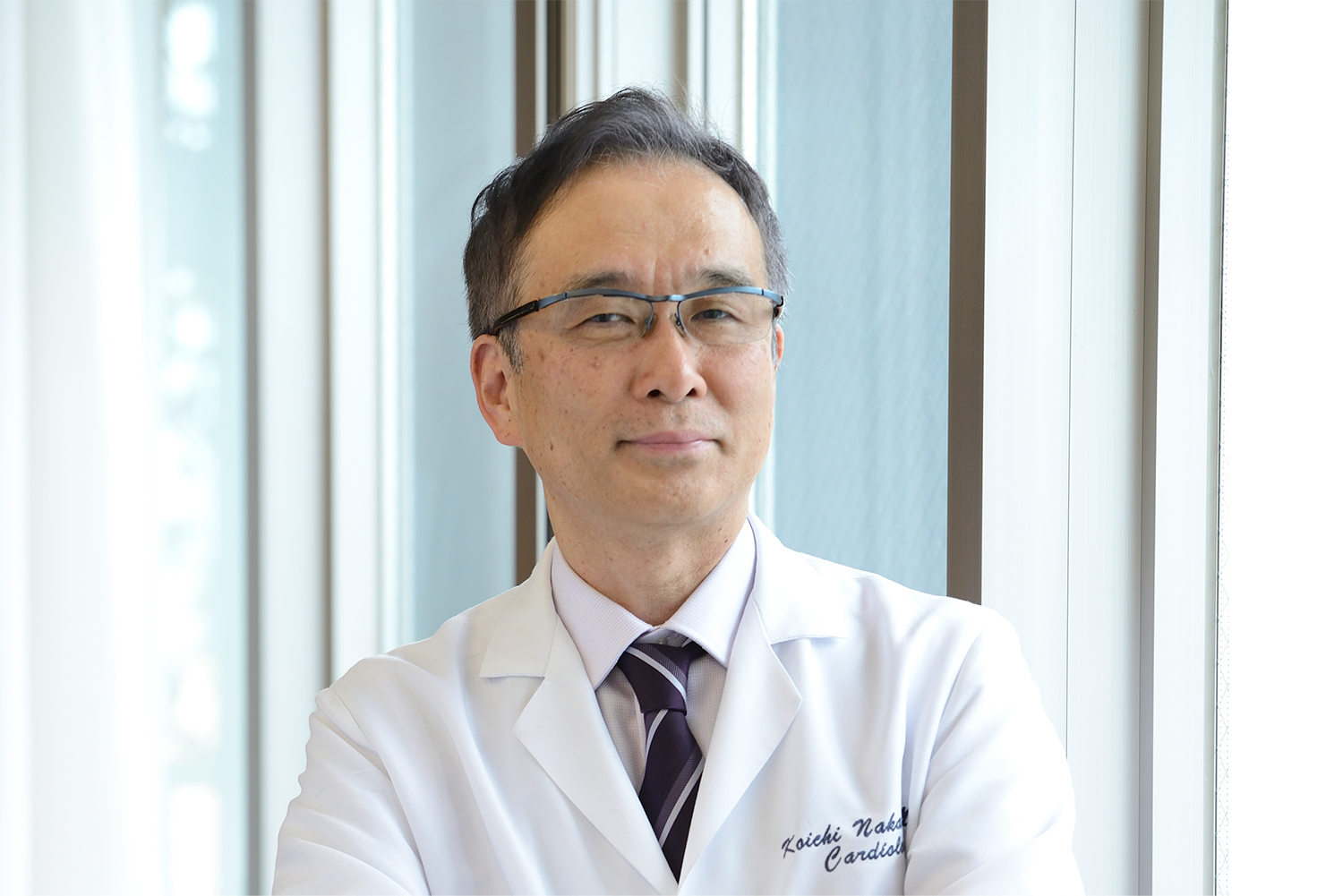イノベーション 2022.12.13
DXで病院運営の改善を――データ活用の重要性と具体策
済生会熊本病院 院長 中尾 浩一先生
新型コロナウイルスの感染拡大によって、世界中でデジタル化の流れが加速しています。日本でも、システムの標準化と共通化を目的とした医療DX*(デジタル・トランスフォーメーション)の推進が始まりました。デジタル化によって医療が“つながり”を持ち始めた今、私たちはその重要性を理解し、覚悟を持つ必要があります。今回は済生会熊本病院 院長 中尾 浩一(なかお こういち)先生から、済生会熊本病院における医療DXの実際を伺います。
*医療デジタル・トランスフォーメーション:データとデジタル技術の活用によって顧客や社会のニーズを把握し、サービスやビジネスモデルを変革して医療における課題解決を図ること。
医療分野におけるDXの課題
医療機関におけるデジタル化浸透
厚生労働省は、ICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)によって医療機関などの情報連携を促進し、地域全体で質の高い医療を提供する仕組みづくりを進めています。2022年10月12日には、岸田 文雄(きしだ ふみお)総理によって医療DX推進本部が発足しました。全国医療情報プラットフォームの創設や電子カルテの標準化を推進するとのことですが、実現は決して容易なものではないでしょう。
和を重んじる私たち日本人の国民性が、真実をありのままに突きつけるデジタル化浸透の妨げとなっているように思います。日本には全人的医療*という言葉もあるように、患者さんは医師との“接触・対面”を好み、医療に温もりを求める傾向にあります。政府が進める医療のデジタル化は、情緒的な日本のアナログ医療と逆行するものなので、浸透のためには、まず国民の価値観から変える必要があるかもしれません。
*全人的医療:特定の臓器や部位にのみ着目するのではなく、心理状態や社会的側面なども考慮しながら、その患者に適した医療を行う方針のこと。
病院運営に関するデジタル技術活用

当社購入素材
デジタル化を目指すといっても、ただ電子機器を取り入れただけではデジタル化とはいえません。医療現場での電子機器導入といえば電子カルテを想像する方も多いでしょう。しかし、電子カルテに各々が今までどおり自分の価値観で物事を書き進めていては、紙がパソコンに代わっただけの話で終わってしまいます。重要なのは、その後のデータ解析と共有です。
とはいえ、デジタル化には電子機器の導入が前提であることも事実です。厚生労働省が発表したデータによると、2020年における一般病院全体での電子カルテシステムなどの普及率は57.2%にすぎません。普及しなければ、データも集まらず活用方法に関する議論も進められませんから、まずは医療界における電子機器の積極導入が急務ではないでしょうか。
そして国が進めている医療DXは、情報共有によって医療界が“つながる”ことを目的の1つにしています。“つながる”というと聞こえがよいですが、概して言えば自分のしたことを他人に見せるということですから、相当の覚悟が必要です。また、当然費用もかさみますので、誰がどう負担していくかというのも課題でしょう。
済生会熊本病院における医療DX、3つの施策
当院はデータに基づく医療を経営の神髄としており、2024年までの中期事業計画として「デジタル化を基盤とした価値中心の医療の創造」を掲げました。デジタル化を進めるにあたっては、JCI(Joint Commission International:国際医療機能評価機関)の評価基準に基づいて仕組みづくりを行っています。たとえば、当院ではJCI基準に則って電子カルテの記入方法を統一しています。これによって患者さんが診療科を移った際にもスムーズに情報共有ができるようになりました。ここでは、当院の中期事業計画に関する具体的な3つの施策を紹介します。
データ分析技術の活用
当院では医療安全管理・品質管理の維持にデジタル分析技術を活用しています。このデータの収集と解析にあたっては、臨床現場には直接関わらないTQM(Total Quality Management:総合品質マネジメント)部が担当しています。
たとえばオリンピックの走り幅跳びなどの競技では、選手が飛んだ距離を自己申告してメダルをもらっているわけではありませんよね。距離の測定やルールに則っているかの判定は第三者によって行われます。当たり前のようなことですが、現状の医療においては第三者による評価体制が未完成だと言わざるを得ません。実際にJCIでも、データ収集方法の決定から実際の分析までは現場と切り離された部署の担当者が行うようQPS(Quality Improvement and Patient Safety:質の改善と患者安全)で定められています。これは人間の弱さを前提とした、“性悪説”ならぬ“性弱説”の考え方に基づくものだといえます。
分析されたデータはTQM部によって共有され、臨床スタッフが確認します。患者さんの状態が悪化したケースや手術後に予定外で集中治療室へ入ることになったケースがあるとTQM部から指摘が入るので、当初は現場からの抵抗を感じました。誰でも、一生懸命行ってきたことを結果だけで判断されたくない気持ちはありますから、これは人情だと思います。実際、患者さんの予後というのはさまざまな因子が関与し、決して医師の技術だけで決まるものではありません。ただし、どのようなときでも医師は自身の判断に対する説明責任を負う必要があります。だからこそ、当院はTQM部が中心となって説明責任を果たすための仕組みを構築しているのです。改善策を話し合う際も、現場に任せきりにはせずTQM部が必ず介入しています。
デジタル化の第一歩は、データを俯瞰的にみることです。そして、データの収集から分析は第三者が行い、現場は分析されたデータの原因を考え改善を実行する、そういったストーリーを考えることがDXの基本だと考えます。
オンライン・リモート技術の活用
当院では“高度医療”を基本方針の1つとして、遠隔地や過疎地の患者さんに対する治療の提供にも力を入れています。特定領域を専門とする医師のいない地域に住む患者さんや海外在住の患者さんでも支援できるようなオンライン診療とインフォームド・コンセント*の体制づくりを進めています。

当社購入素材
*インフォームド・コンセント:自身の症状や今後の治療内容について患者さん本人とご家族に説明を行い、納得したうえで同意を得ること。
RPAの活用
日々の定型業務に関しては、RPA(Robotic Process Automation)化を行っています。RPAとは、事務的なタスクをコンピューターに覚えこませて自動的に処理するシステムを指します。コストの面で課題はありますが、今後はおそらく下がってくると考えられますし、コンピューターのサポートによって、人でなければできない仕事を適正な業務時間内に行うことができるようになれば、医療者の業務効率化につながります。
以上のように、データ分析技術、オンライン・リモート技術、RPAなどを駆使しながらデジタル化を進めていますが、技術が進歩しても、それを使う現場の人間にデジタルリテラシーがないと本当の意味での実現は難しいといえます。デジタル化の完成にはもう少し時間がかかりそうですね。
慢性期医療における医療DXの可能性

当社購入素材
急性期医療を担う当院は、慢性期医療を担う施設との連携が欠かせません。そのうえでも客観的な分析・データ化は重要視しています。具体的には連携先の病院に転院した患者さんの予後や、紹介を受けた患者さんの手術率です。当院は紹介受診に重点を置いた急性期医療機関ですから、地域の中で任された役割を果たすには、まず現状の理解が必要です。
今後、医療DXの浸透によって地域がつながりを持ち、タイムリーに患者さんを送れる仕組みづくりができることを願っています。患者情報の共有だけでなく、患者さんの容体に変化があれば自動アラートで紹介元にも連絡がくるなど、地域全体で患者さんをサポートするシステムが理想ですね。また、日々変化する治療のスタンダードや新薬の情報を地域内でタイムリーに共有できれば、地域における医療レベルの向上も期待できます。
また、医療DXは課題改善ツールとしても活用できるかもしれません。たとえば日本の医療には、検査すればするほど患者さんに感謝されるという特徴があります。少子高齢化による医療費高騰が叫ばれている今、検査過剰になりがちな現在の医療体制を変えていかなければなりません。
そのためには、医師・患者関係において、その検査に対する費用の出所について共に考えていくことが重要です。SDM(Shared Decision Making)が行える環境を整え、過剰な検査・診断・治療が行われた際には、医師や患者さんにフィードバックが行われる仕組みづくりができれば、将来的には医療費の削減にもつながるのではないでしょうか。