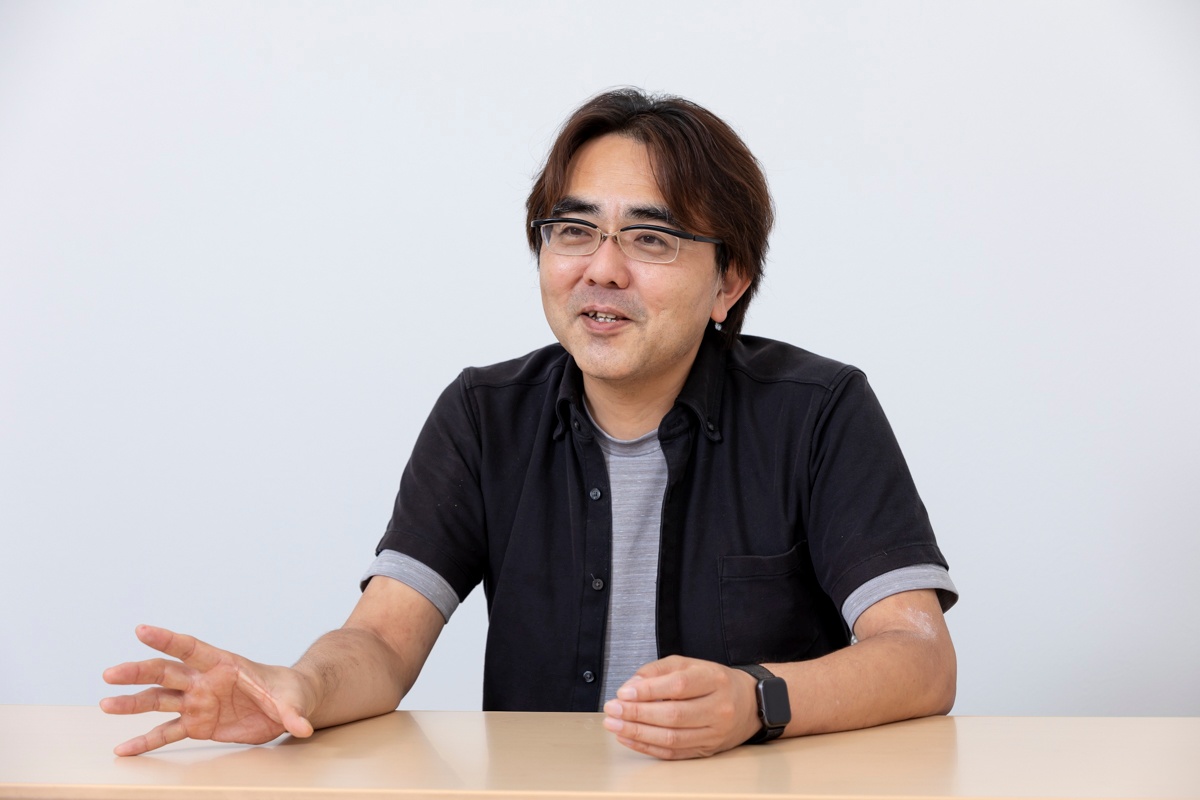イノベーション 2024.05.15
日本循環器学会におけるSNS活用の仕組み――持続可能で安定した運用に向けて
日本循環器学会 情報広報部会長 岸 拓弥さん
海外では情報発信ツールの1つとしてソーシャル・ネットワーキングサービス(Social Networking Service:SNS)を活発に使用する医療系学会があり、近年、日本でもSNSの運用を開始する学会や医療機関が増えています。医療はセンシティブな情報を含むため、SNSを運用するにあたっては手軽さと専門性のバランスを考えた舵取りが必要になります。そのようななかで、約7年にわたってSNSをうまく活用しているのが日本循環器学会です。今回は、日本循環器学会において情報広報部会長を務められた岸 拓弥(きし たくや)さん(国際医療福祉大学大学院 医学研究科(循環器内科学)教授)に、SNS活用のコツやこれまでの運用を振り返って感じることなどについてお伺いしました。
SNS活用にあたって ――“誰”を対象に、“何のために”発信をするのか
日本循環器学会では、医療従事者に向けて2017年よりX(旧Twitter)を活用した情報発信を行っています(日本循環器学会 情報広報部会X公式アカウント:@JCIRC_IPR)。発信している内容は、主に学術集会の様子や公式のジャーナルに掲載されている論文、ガイドラインの引用など医療従事者に向けた学術的な情報です。当学会や循環器医療について少しでも多くの人に興味を持ってもらうため、特に学術集会中のリアルタイム発信に力を入れています。
SNSを活用するにあたって、私たちはまず“誰”を対象に“何のために”発信するのかという目的を明確にするところから始めました。“誰”という対象は、一般生活者と医療従事者の大きく2つに分けられます。一般生活者に向けた啓発活動はとても大切なことですが、医師の発言や情報発信で一般生活者の意識や行動が変わるのは難しい側面があります。たとえば、有名なインフルエンサーが「薬を飲みましょう」と発信すれば、影響を受ける人も大勢いるでしょう。対して私たち医師が同じことを言っても、残念ながらインフルエンサーを超えられるほどの影響力はありません。悩んだ末、当学会では“医療従事者”を対象とすることに決めました。
SNS運用の目的については、当学会のホームページへアクセスしてもらい“最新版のガイドラインをダウンロードしてもらうこと”としました。循環器医療に興味を持った人たちがガイドラインを読み、よりよい医療を提供してくだされば間接的に社会へ貢献できると考えました。
“失敗しない”SNSの運用のコツとは――当たり前のことを継続できる体制を作る
学会や医療機関の代表であることを自覚した発信を
公式SNSを価値あるものにするためには、安定した運用ができる“ルール”を作ることが大切です。安定した運用とは、いわゆる“炎上しない”運用です。SNSは誰でも簡単に情報発信できる便利なツールですが、利用には一定のインターネット・リテラシーが求められます。ましてや発信する情報が医療となれば、なおのこと注意が必要です。ごくごく当たり前のことではありますが、学会として世に情報を発信する以上、おざなりにすることはできません。
当学会では、“プライバシー保護”“関連法令の遵守”などSNS利用における5原則を定めています。加えて、“有益で正確な情報を投稿する”“投稿内容が記録として恒久的に残ることを認識して投稿する”など投稿に関するルールも定め、これらに則って運用しています。患者さんが特定できるような内容や差別的な内容を投稿しないのはもちろんのこと、投稿する論文1つとっても慎重な判断が求められます。当学会のSNSで投稿する論文は公式ジャーナルに掲載したもの、つまり学術的に確立されたもののみです。医療は日々研究が進んでおり、なかには一般生活者でさえも興味を抱くような革新的な論文もあるでしょう。ただ、研究が進んだ結果その論文が誤りだと判明する可能性もあり、その場合は学会が間違った情報をSNSで広めたことになります。医療系学会や医療機関のSNS運用の際は研究などが進んだ“先”の責任まで考えて投稿しなければなりません。
精通した人が土台を作り、持続可能な仕組みにする
学会や医療機関がSNSを開始する際、若手会員や医師に立ち上げから運用までの全てを任せるケースをたびたび目にします。SNS=若者というイメージがあっての体制だとは思いますが、正直おすすめの方法とはいえません。たしかにプライベートでSNSになじみがあるのは若手かもしれません。ただ、法律を遵守し、学術の信ぴょう性を判断する必要があることを考えると、若手のみではまず難しいと思います。現場が楽しそうにしている様子など医療情報が含まれない内容であればおそらく炎上はしにくくなりますが、そうなると今度はネタ切れになってアカウントの発展は難しくなるでしょう。安定した運営を維持しつつSNSを発展させるためには、“医学・法律・SNS”全てに明るい人材が牽引していく必要があると考えます。また、アカウントの立ち上げをした後は、“誰でも”安定した運用ができる仕組みを作ることも大切です。いくら安定した運営ができていても、精通した人物がチームから抜けた時に崩れてしまうのでは意味がありません。フローやルールなどを整え、誰がやっても変化なく運用ができるような体制を構築する必要があります。
当学会では学会公式SNSの立ち上げの時こそ私をはじめSNSに精通したメンバーが関わっていましたが、上記のルールや体制が確立した現在、運営は全て事務局に任せられるようになりました。あくまでガイドラインのダウンロードを目的としているため一際(ひときわ)目立つような発信をする必要はありませんし、内容についてもルールに則って投稿をするのみなので、私が何をせずとも安定して運用できる仕組みになっています。
SNSは人を幸せにするもの――7年間のSNS運用を振り返って
最近は、SNSの運用についてほかの学会や医療機関から相談を受けることも多くなりましたが、まず考えるべきは“本当にやる必要があるのかどうか”という点です。周りに倣(なら)って何となく始めたとしても安定した運用は難しくなりますし、もし炎上した場合は誰も幸せにならない結果となってしまいます。やはり公式SNSは誰かを笑顔にしたり喜ばせたりするためにやるものだと私は思います。過去に当学会のSNSを活用している会員から「育休中に育児や家事をしながらでも学術集会を体験できた」「がんの治療中だが、討論の内容を知ることができてとても楽しかった。病気を治して学術集会にまた参加したいと思った」などという声をいただいたことがあり、こちらまでうれしくなりました。
「学会SNSの最適解は何か?」と問われると正直答えは分かりません。当学会はもともと会員数が多く、ガイドラインも無料で公開されています。この環境があったからこそSNSをうまく活用できたと思いますし、日本循環器学会ができていない一般生活者を対象としたSNS活用に成功している学会(日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会など)もあります。これから学会公式SNSの活用を考えている、あるいはフォロワー数が伸びなくて困っている(そもそもフォロワー数がどれくらい必要なのかは考えないといけませんが)のであれば、まずは目的をきちんと決め、同じ目的で先行してSNSを活用している学会の方法を真似してみることをおすすめします。“人を幸せにするもの”ということを忘れず、本当に必要なのであればぜひ情報発信に取り組んでみていただければと思います。
時代に応じたツールで“安心感”を届けたい
今後、情報発信の手段は時代に応じて変わっていくことでしょう。今はXをはじめとするSNSの利用者が大勢いますが、もしかしたら10年後はまったく異なるプラットフォームが主流になっているかもしれません。いずれにせよ、その時代においてベストと思えるツールを使って「日本循環器学会のアカウントをフォローしておけば循環器に関する最新情報や学会の空気感が分かる」という安心感を届けていければと思います。私個人としては、2035年に100回目を迎える学術集会の場で「10年くらい前にSNSを頑張っていた岸先生っていう人がいるらしいよ」「あの時はSNS頑張ったね」など、この時代を知っている人も知らない人も含めて歴史の1つとして有意義に振り返ることができたらうれしいです。