キャリア 2019.06.28
会社員から理学療法士、そしてリハビリテーション室長へ−西田好克さんのあゆみ
芳珠記念病院 西田好克さん
石川県能美市にある芳珠記念病院において、同院リハビリテーション室 室長として活躍する西田好克さんは、大学を卒業後に一般企業の会社員として働いていましたが、夢を諦めきれず、理学療法士に転身されました。現在は、芳珠記念病院が属するほうじゅグループの全てのリハビリスタッフをまとめる管理者として、ご活躍されています。西田好克さんに、これまでのあゆみや理学療法士として印象的だった出来事などについて、お話を伺いました。
Q どうしてリハビリの世界で働くようになったのですか?
- リハビリに興味を抱くも、大学受験で桜は咲かず
高校生で進路選択をする際、仕事や資格にかかわる本をたくさん読みました。そのなかで、人の人生にかかわるリハビリという分野を知り、強い興味を抱きました。
その後、金沢市内の国立大学を目指して受験勉強をしたのですが、残念ながら試験に落ちてしまいました。それでも諦めきれず、1年間浪人して再度入学試験に臨みましたが、このときも桜は咲かず。さすがに2浪はできないと思い、合格した国立大学の工学系分野に進みました。
- 大学卒業後は製造業の会社で品質管理などに携わる
大学で工学を学んだのち、製造業の会社に就職しました。そこでは、品質管理などさまざまな業務に携わりました。充実した毎日でしたが、時折、パソコンに向かっている時間をどうしても苦痛に感じることがありました。会社員として働く間もずっと、「人の人生にかかわる仕事をしたい」という気持ちは強かったように思います。
- 脳梗塞で倒れた祖父を介助する両親を見て、リハビリへの思いが再び湧き上がった
私が会社員として働いていたときに、祖父が脳梗塞で倒れました。病院での治療を終えて自宅療養となった祖父の家へ、両親と何度もお見舞いに行きました。
祖父は、脳梗塞の後遺症として手足の拘縮(こうしゅく:関節が動きにくくなり可動性が制限されること)などが残り、思い通りに動くことができない状態でした。両親は、お見舞いのたびに、祖父を介助しながら、固まって開かない祖父の手を祈るように繰り返しさすっていました。
そのような両親の姿を見て、自分の無力さを感じると同時に、「リハビリの仕事をしたい」という思いが、再び湧き上がりました。ちょうど27歳になる頃で、「挑戦するなら今しかない」と、金沢にできた専門学校に入学して勉強を開始。そして、無事に理学療法士の資格を取得することができました。
Q これまでに印象的だった患者さんはどのような方ですか?
- 上肢機能を回復させたいと、一緒にリハビリをがんばった患者さん
リハビリの仕事に就いて1年目の終わりに担当した患者さんは、中心性頸髄損傷(外傷性頸髄不全損傷のうち、下肢よりも上肢に強い運動障害・感覚障害をきたす症候群)でした。60歳代の方で、もともとは大工として元気に働いており、手先を使う趣味をお持ちでした。手先が元通り使えるようになりたいというご希望をお持ちでしたので、私たちもなんとかして上肢機能を回復させようと、一緒にリハビリをがんばっていました。
退院時には、ひとりで散歩できるくらいまでには回復しましたが、結局、手を使う仕事に復帰するのは難しく、患者さんの希望を叶えることができませんでした。それでも患者さんは感謝してくださり、それから現在に至るまで、10年以上にわたり、ことあるごとに病院に顔を出してくれます。そして最近、手を使う趣味を新たに始めたと教えてくれました。それは本当に嬉しい知らせでした。
しかし、患者さんの希望を叶えることができず、自分の限界を感じたことは、臨床経験でとても大きい出来事です。非常に悔しく、自分の力不足を認識して、もっとがんばらなくてはいけないと強く感じました。

- 最期まで希望を持ってリハビリに打ち込まれていた患者さん
もう1名の方は、重篤な循環器系の疾患を発症し、急性期病院から転院されてきた、40歳代の患者さんです。転院時には、チューブやドレーンなどがいくつも体からつながっている状態で、意識こそはっきりしていたものの、予後は1年ほどといわれていました。
その方は身長が200cm近くあり、病院のベッドにはおさまりませんでした。通常のベッドでは小さすぎて転院前の病院では、脚を折り曲げるようにして就寝していたそうです。一晩寝ると体の節々が痛くなる、と不満を口にされていました。
そこで、まず私たちは、脚を折り曲げずに就寝できる環境を整えることにしました。病棟の管理者に掛け合って、大きな台を用意し、ベッドの足側の柵を外して、そこにその台を設置しました。台を利用してベッドの長さを延長できるようにクッションとシーツでなんとか特製ベッドを完成させました。患者さんは足を延ばして寝ることができるようになり、「すごく楽になった」とたいへん喜んでくれました。
その後、離床を目指して根気強くリハビリを続け、ようやく体を起こせるまでに回復しました。そこで、転院してから初めて、病室の外に出てみました。すると、病室を出た途端、患者さんの顔がパッと明るくなったのです。今でも、その瞬間を忘れることができません。私は嬉しくなって、患者さんと共に病棟をまわり、「病室から出られましたよ!」といろいろな人に伝えて歩きました。この出来事は、患者さんのリハビリへの意欲につながったようで、翌日からは、今まで以上にリハビリに励んでいました。
最終的には、その患者さんは当院で息を引き取りました。亡くなられた後にわかったことですが患者さんの弟さんによれば、本人も含めて、ベッドから起きられるようになるとは夢にも思っていなかったようです。それが少しずつ動けるようになってくると「自分で歩けるようになって、外に出たい」と、最後まで希望を持っていたそうです。私は、ご本人の口から直接そのような言葉を聞いたことがなく、とても驚きました。黙々とリハビリに励む患者さんの姿を思い出し、患者さんにそのような強い想いがあったのだなと、改めて心を打たれました。
あまり長くはない私の臨床経験において、患者さんの終末期にかかわることができたことは、その後の自分の大きな糧になりました。
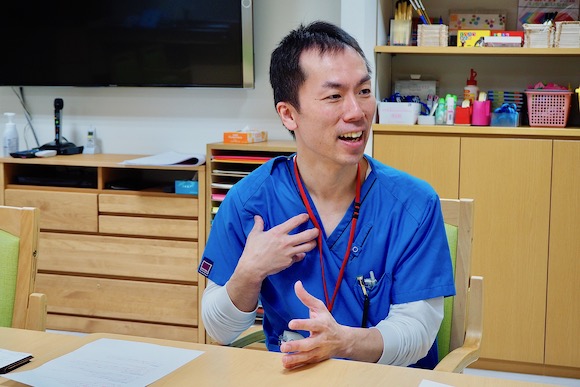
Q 一緒に働くリハビリスタッフへのメッセージをお願いします
社会が大きく様変わりし、医療分野においても「治す医療」から「支える医療」へとパラダイムシフトが起こっています。このような流れのなかで、これからのリハビリには、患者さんを治す(回復させる)という必須条件に加え、「その後の人生をどのように支えていくか」という視点も大切になっていくと思います。私は、このような視点を大切にして、これからも職員のみなさんを鼓舞していきます。
指示を待っているだけでなく、能動的に行動して、ぜひ大いに活躍してください。自分から意見を発信し、枠組みから構築することは、得られる裁量も大きく、とても面白いことです。















