病院運営 2025.11.27
在支病として地域をつなぐ役割を担う――板倉病院の都市型地域包括ケアシステムとは?
板倉病院 理事長・院長 梶原 崇弘さん
核家族や独居の高齢者が増え、住民間の関係が希薄な傾向にある都市部では、地域の健康を守る医療ネットワークの構築が課題です。板倉病院 理事長・院長 梶原 崇弘(かじわら たかひろ)さんは、都市部における地域包括ケアシステム*を構想し、地域の医療機関との連携強化をはじめとしたさまざまな取り組みを行ってこられました。「地元への愛着が活動のベースにある」と語る梶原さんに、“都市型地域包括ケアシステム”構築への思いや今後の展望などをお伺いしました。
*地域包括ケアシステム:要介護状態となっても住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、住まいや医療、介護、生活支援などが一体的に提供される仕組みのこと。
板倉病院が目指す都市型地域包括ケアシステムとは?
千葉県船橋市は、東京駅から電車で約30分と都内からアクセスがよいのが特徴です。人口はいまだ増加中で、高齢者の人口も増加傾向にあります。そんな船橋市に位置する当院は、地域密着型中小病院として、救急や予防、在宅医療と、多様な医療サービスを提供してきました。機能強化型の在宅療養支援病院(在支病)でもあり、通院が難しくなった患者さんへの訪問診療を行うほか、在宅医療を支える機能も備えています。
特に、地域の医療機関をつなぐ“ハブ”のような役割を担うことに力を注いでいます。当院はもともと医療法人の中にクリニックや保育園など多様な機能を有しており、シームレスに患者さんを診るという目標を掲げていました。しかし私が3代目の院長に就任した際、全てを自法人で担うのは負担が大きく、質を維持することが難しいと考えました。地域の信頼できる先生方と連携を図りながら、患者さん中心の医療ネットワークを作るほうがよいだろうと思い至ったのです。
それ以降、“都市型地域包括ケア”を目指し、地域における連携を図ってきました。二次救急医療機関や三次救急医療機関、かかりつけ医など、それぞれの役割を明確にしながら、当院のような地域密着型中小病院が各医療機関をつなぎ、円滑な連携の実現に向けて取り組んでいます。
地方と都市部では、抱える課題が異なります。地方では、人間同士の関係が密な傾向にあることが多いでしょう。たとえば住民が隣に住む高齢者を見守るような文化が根付いているなら、それに合った地域包括ケアがあるはずです。一方、船橋市のような都市部は集合住宅も多く、関係が希薄な傾向にあります。住民同士の見守りが不十分という前提で、コミュニティの中心に病院を置き、地域住民同士、そして地域住民と医療機関がいかにつながり、お互いに支え合えるようになるかが、都市型地域包括ケアシステムの鍵となります。
都市型地域包括ケアシステム構築へ向けた取り組み
都市型地域包括ケアシステムを実践するうえで、当院では主に3つの取り組みを行ってきました。
1つ目は医療関係者に向けた取り組みです。たとえば、「C@RNA Connect(カルナコネクト)」といって、当院のCTやMRIなどを開放し、地域のクリニックの医師が無料で利用できる画像連携を行っています。地域の医療機関と連絡を取り合うにあたり「連携していきましょう」と挨拶するだけではなく、当院ならではの個性を出し、意思をしっかりと伝えたいと考えていました。その頃に参加した勉強会で講師を務められていた先生からカルナコネクトの話を聞き、すぐに当院でも実施することにしたのです。このようなサービスを実際に利用していただくことで、連携の強みをより実感してもらえると感じています。
そのほか、連携施設へ端末の貸し出しも行っています。きっかけはコロナ禍に、感染隔離を行っていたホテルで医療用端末を貸し出して、現場にいる職員さんから受診に関する相談を受けていたことです。以降、医療用のスマホを連携施設に貸し出し、たとえば患部を撮影して画像を送ってもらうことで、受診すべきかどうかの判断を遠隔でできるようになりました。その結果、病状が悪化するまで待つことや、受診が不要なのに来院する手間を極力なくすことができるようになったのです。連携することのメリットを感じてもらって初めて地域の医療関係者に心を開いてもらえるという思いから、まずはこうした取り組みを行ってきました。
2つ目は地域住民の皆さんに向けた取り組みです。当院では“健康にあまり興味がないような人たち”に向けたイベントに力を入れてきました。健康に強い関心を持つ人たちだけに来ていただいても、地域住民全体の健康にはつながりにくいと考えたからです。そこで、お酒の飲み方教室やラテアート講座など、あまり病院らしくないイベントを開催してきました。また、ご家族の受診につながればと思い、子ども向けの病院体験実習も行っています。このような取り組みを通じて、地域住民の皆さんに当院のことをよく知っていただき“ファン”になってもらえたらと期待しています。
3つ目は職員に向けた取り組みです。当院では、やるべきこと、やらなくてよいことを明確にし、メリハリを持って働けるような体制を築いています。また、当院が周囲からどう見られているか、職員に積極的に伝えるようにしてきました。公立学校使用の教科書に当院が掲載されたことや、厚生労働省から取材を受けたことなどを知って「ここで働いていてよかった」と職場への誇りを感じてもらえるよう努めています。
今でこそ当院の職員も、医療関係者や地域住民の皆さんに向けた活動に対して、積極的に取り組んでくれていますが、当初はこちらのイメージするものがうまく伝わらず、戸惑いや反発のようなものがあったと思います。しかし、職員一人ひとりにミッションを託し、成功体験が積み重ねられていった結果、主体的な行動につながったと感じています。たとえば、子ども食堂のイベントは、職員からの発案です。ほかにも、職員が主導して「いたくラッコ」という当院のキャラクターを用いた情報発信を行い、いろいろなところとコラボして浸透させてくれています。
今後の展望――ベースには地元への愛着
2024年、当院は地域医療連携推進法人を設立しました。同法人は、地域で良質および適切な医療を効率的に提供することを目指して医療連携推進業務を行う一般社団法人を都道府県知事が認定するものです。これまで推進してきた医療ネットワークをアップグレードしたいという思いで、設立・認定に至りました。一貫して大事にしてきたのは、地域に根差して活躍している人たちと協力体制を築くことです。私は、ここ船橋市という地元をとても大切にしています。同じように地元のことを真剣に考えられるような人柄を重視し、チームの一員として迎え入れてきました。
当院は、地域包括ケアの中心を担えるような在支病として、住民の皆さんを適切な医療サービスにつなげたり、健康寿命を伸ばしたりという目線で都市型地域包括ケアを実践してきました。地域医療連携推進法人の設立を通じて行政との連携も強くなり、地域全体でまちづくりについて意見交換できるようになったのは大きな成果です。
このような活動に力を注いでこられたのは、船橋市への愛着がベースにあるからだと思っています。そのうえで、自分の取り組みによって誰かが喜んでくれるとうれしく、私のモチベーションにつながっていると感じています。
今後の展望としては引き続き、船橋市の地域包括ケアのモデルを行政と共にアップデートしていくつもりです。また、最近の医療業界の賃金の伸び率の低さなどを鑑みると、医療は崩壊の瀬戸際にあると思っています。仮に私たちを取り巻く環境が大きく変化した場合でも、安定して運営できる当院のようなモデルを確立していく必要性を証明したいと考えています。
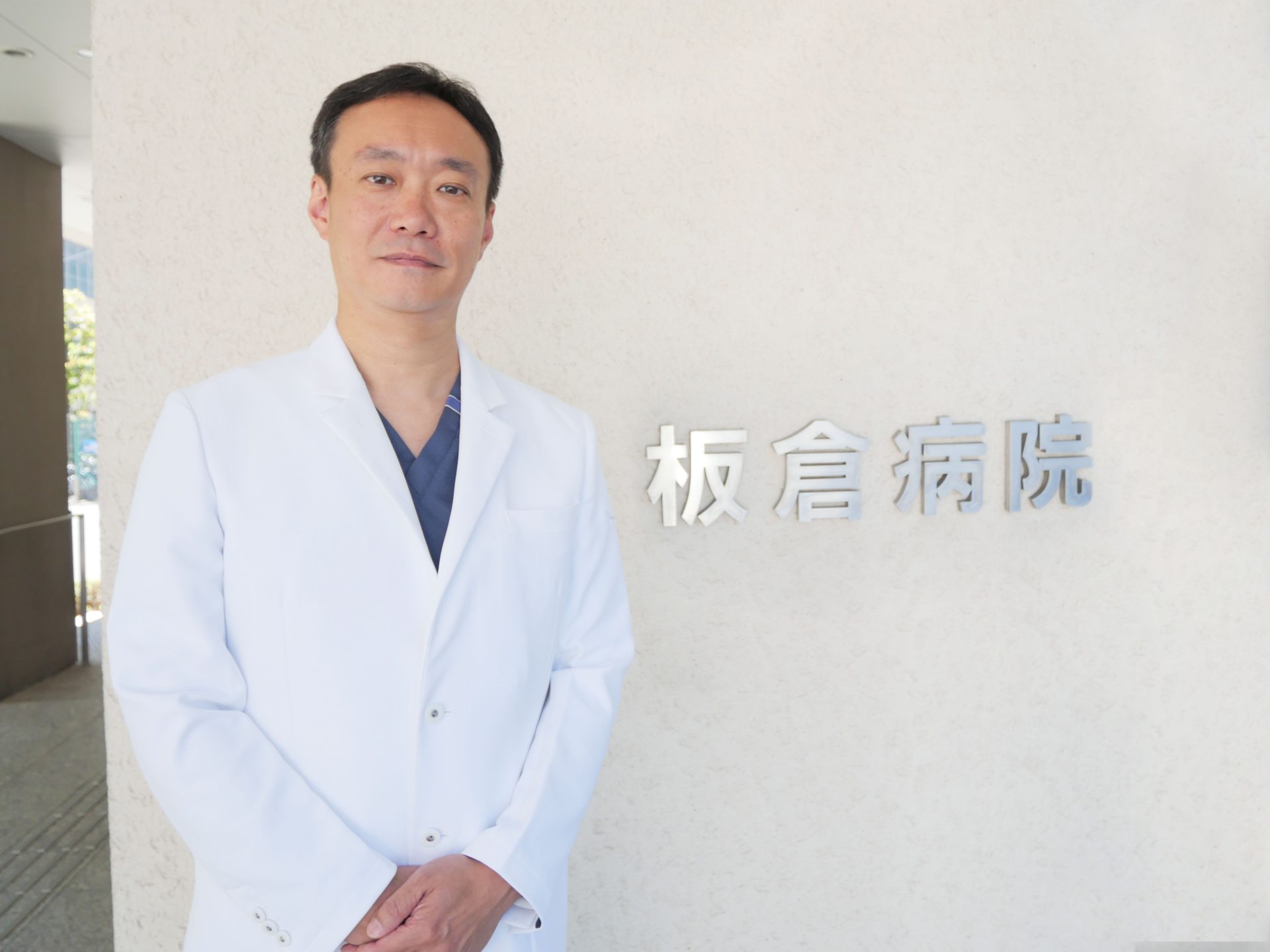
読者へのメッセージ
現在、日本が直面している慢性期医療の課題というのは、高齢化社会を迎えるとともに医療の質が向上したことによる、誰も目にしたことのなかった景色だと思います。
超長寿化して医療のレベルが上がったために亡くなる人が減り、糖尿病や高血圧などの慢性疾患、認知症などを含む慢性期の病気が増えたのでしょう。“治す医療”から“治し支える医療”の必要性が増すと思います。
また、医療者側の教育だけではなく、患者さんやご家族の教育も重要になると考えています。元気なときからACP(Advance Care Planning:本人による意思決定を支援する取り組み)を始めて将来に備えることが、本人の意思を反映した看取りや療養につながっていくのではないでしょうか。多職種の連携も大切になるでしょう。
先に述べたように、当院のような在支病、域密密着型中小病院は “ハブ”として地域をつなぐ役割を担っています。これからも、こうした連携の輪の一員として共に活動していきたいと思いますし、気軽に同院を活用していただけたらと思います。















